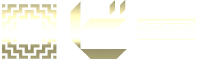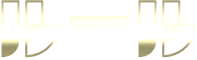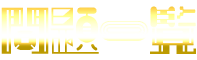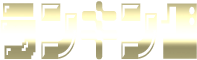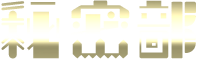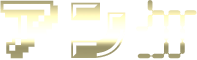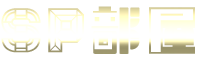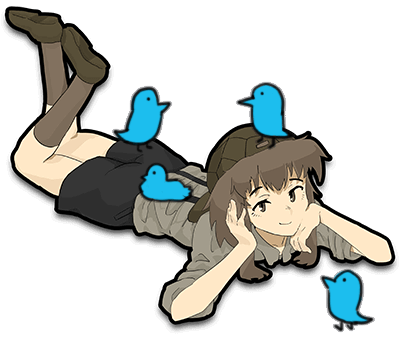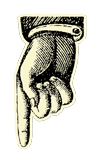漫画が大好きな高校生のタクヤと、そんな彼に密かに思いを寄せている友達のイズミ。
二人はよく同じ漫画を読み、その感想を言い合っていた。イズミがタクヤのところを尋ねるたび、二人で読む漫画を示し合わせ、次に来たときにその感想を熱く語り合うのだ。
そんなある日、次の漫画はどれにしようと二人で話しているとき。イズミが最近流行りのギャグ漫画を提案したため、タクヤは大声で彼女に怒りをぶつけた。
実は、イズミは『タクヤがあまりギャグ漫画が好きではない』ことを知っていたのだが、では、なぜそれを知っていながら、イズミはそんな提案をしたのか?
解説を見る
要約:
余命僅かなタクヤに、最近流行りの、つまり未完結のストーリー漫画を勧めるのを躊躇ったイズミは、どこで読めなくなってもいい一話完結のギャグ漫画を提案した。
——————
ああ、イズミ。今日は早かったな。
白く無機質なドアをそっと開けた先には、タクヤがいつも通りの笑顔で待っていた。今日は6限が自習だったから、と返す私は、多分全然笑えてない。
入院着の袖の先からのぞく真っ白な腕を見て上手く笑えない自分が、嫌いだった。だから、なんとかそんな思いを振り切って、今日の出来事を話していく。
数学の抜き打ちテストが難しすぎたこと。
休み時間についつい眠りに落ちたこと。
体育のサッカーの授業で、初めて一点、決められたこと。
どんな他愛ない話でも、嬉しかった話でも、タクヤは目を輝かせて聞いてくれる。冗談混じりに話を広げられ、つい話し込んでしまう。この時間がとても楽しくて大切で、愛おしい。そう気づくとしかし、その思いがどんどん萎んでいく。
タクヤはそうして、いつもの漫画の話に移った。私たちはいつも、連載中のものの中から同じ漫画を示し合わせて読み、感想を言い合うことを楽しみにしていた。漫画をよく知らない私は、いつも率直な感想しか言えなかったけど、何よりも楽しそうに話を広げてくれるタクヤが見られるのが嬉しくて、自然と漫画も好きになっていった。
定期的に、この病院に尋ねるたび、そんな感想を言い合う時間は続いた。この前読んだのは、サッカー漫画『オンサイド』の最終回。ついこないだ完結した分を読んで、その余韻に二人で浸り切った。
主人公の熱い勝負魂。
大会決勝の相手の稀代な戦術。
何度ボールを奪われても諦めないチームのガッツ。
そして、全てを締めるにこれ以上ないラストシーン。
時間という概念がもしなかったら、私たちは一生語り合えたかもしれない。二人でずっと、冊子を指差し、セリフを真似し、その興奮を吐き出していた。楽しさ以外の嫌なもの全てを忘れて、笑いながら感想を言い合った。
やがて、そろそろ帰らなければならない時間になったことに、タクヤの指摘で気づく。
寂しい。もっと一緒にいたい。言葉を必死に飲み込んで、そうだね、と私は立ち上がった。
なあ、次は何にする?
タクヤに言われ、私は固まった。道中でずっと抱えていた憂鬱が、興奮を吐き出した分だけ、再び全てなだれ込んでくる感覚。そしてその憂鬱は、真っ黒な哀しみに変わっていく。
振り返ると、立ち上がって少し距離を取った分、タクヤが一層小さく見えた。入院着、ベッド、繋がれた管。私の心とは真逆の真っ白さ。タクヤの生を必死に支えるのと引き換えに、さっきまでの幸せな時間を吸い取っていく管。
最近さ、『〇〇〇』っていうギャグ漫画が流行ってるみたいでさ。
口にしてしまってから、すぐにそれを否定したい気持ちに襲われた。
こんなこと、言いたくないのに。でも、言わないことも苦しかった。
…なんで、それを読みたいと思ったんだ?
タクヤが無機質な口調で尋ねる。でも、その答えは、きっとタクヤには全部お見通しだと悟った。こんなに、こんなにずっと一緒にいたんだから。
その漫画を読みたい理由なんてどこにもない私は、口篭る。どうしよう、やっぱりダメだった、なんて言い訳しよう。そう考えるより先に、タクヤが口を開いた。
手軽に読める、一話完結の話だからだろ。
真っ黒な心に、篠よりも鋭い何かが刺さった。
でもそれを刺したのは、タクヤじゃない。私。
連載中のやつの中で、未完結のストーリーじゃなくて、一話完結の話だったら、俺がいつ「漫画を読めなくなって」も、続きが気になって苦しむことがないと思った。
だからだろ。じゃなきゃ、ギャグ漫画があんまり好きじゃない俺にそんなの、おすすめしない。
こっちを睨んでくるタクヤの顔を見て、涙なんて出なかった。真っ黒に染まっていた心が、それが真っ黒なことさえ気付けないくらいに、感覚を失っていく。
ごめん。タクヤが、心配で。
違う。そんな薄っぺらなことが言いたいわけじゃない。わけじゃないのに。
心の中は真っ黒で、その中で何を探しても言うべき言葉が見つからない。するべきことが見つからない。なんて言えばいいのか、わからない。
お前、『オンサイド』ちゃんと読んでないだろ。
そう言われて、全身に黒い血液が流れ出すような感覚に襲われた。でも、首を振る勇気も、力も出ない。
2-1の劣勢、最後のロスタイムまで、ボールにしがみついたチームの情熱とか、励まし合いの言葉とかさ。
それだけじゃねえ。今日、体育の授業で、一点取れて嬉しかったって。『オンサイド』みたいだったって。お前言ってたけど。
それ全部、嘘だったんだな。
そこまで言われて初めて、余命幾ばくかも判然としないタクヤの、「心配」をしていた私が、どんなに身勝手なやつだったか、全て、わかった気がした。
早く帰れよ。
目の前のタクヤが言っているとは思えない大声が響いた。私は振り返ることもなく、その場から逃げ出した。
——————
その翌日だった。
私はタクヤの病室のドアを開け、驚く彼のもとへ駆け寄った。
普段は毎日訪れることはなかなか叶わなかったけど、今日はそんなことを気にしている暇はなかった。
私は昨日、今までで一番、タクヤに残酷なことをした。タクヤの気持ちを考えた気分に浸って、勝手に自分の心を黒く塗りつぶしていた。そのどす黒い絵の具を、しまいにはタクヤにまで塗りつけてしまった。
私からも、タクヤからも、あと少しの大切な時間を奪い去ろうとした。
だからこそ、早く言わなきゃ。
ただ謝るだけじゃない。それは、もう一度ピッチに戻るだけ。一度ピッチから逃げ出した私は、また最後まで走り続けなければならない。
ロスタイムの間だけでもいい。最後のたった一秒だっていい。
私たちの大切な時間を、私自身の言葉で取り戻すんだ。
ずっと隠していた、隠さなきゃと思っていた、タクヤへの思い。一緒にいた時間の中で、タクヤだってその気持ちが同じなのは、前から気づいている。
でも、それをすぐに失って哀しむのが怖かった。
せっかく一緒になれたとわかったのに、愛しいと思い合えたのに、それがすぐに崩れ去ることを知っているのが怖かった。
でも、本当はそうじゃない。
一緒にいられない方が、嫌に決まってる。
私は、目の前にいるタクヤに、彼への思いの全てを吐き出した。
その思いは、真っ白なんかじゃない。一歩間違えば真っ黒に見えるくらいに極彩色な私たちは、ただの真っ白な友達なんかじゃない。
もっと一緒に、近く、に、いたいから
叶うなら、あと少しの間、だけでも、もっと近くに
ずっと、前、前から
私は、私はタクヤの
ことが
——————
ありがとう。
五彩に映ゆる、タクヤの心の鼓動を知覚しながら、私は、少しずつ、ゆっくりと、呟いた。
トリック:1票物語:5票納得:1票良質:3票
物語部門
ベルン>>
(改めて読み返してみると、いいなぁ...!ってなりましたっ!)
輝夜>>
こういう物語のあるスープ、好きです。「怒りをぶつけた」という感情が重要な要素でありながら、納得感を失わせないのはさすがです。
霜ばしら>>
難しいテーマで、私には登場人物たちの心情が複雑に感じられて理解しきれていないところもあるのですが、それでもイズミの想いはぐっと胸に迫るものがありました。